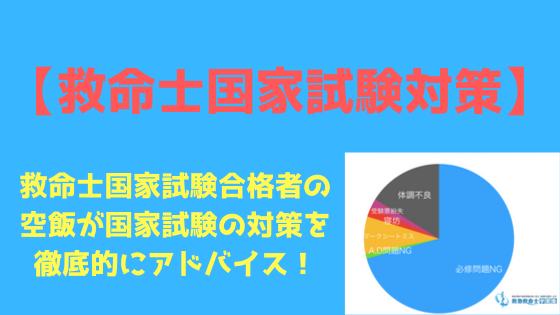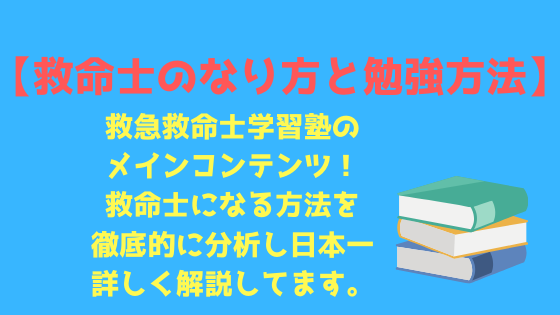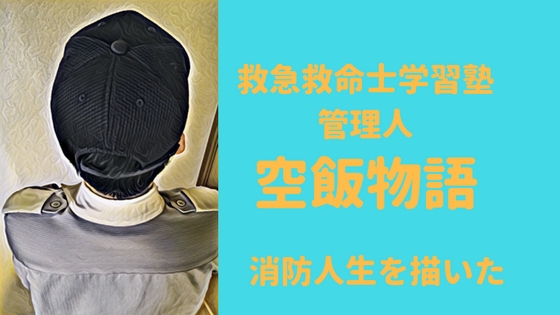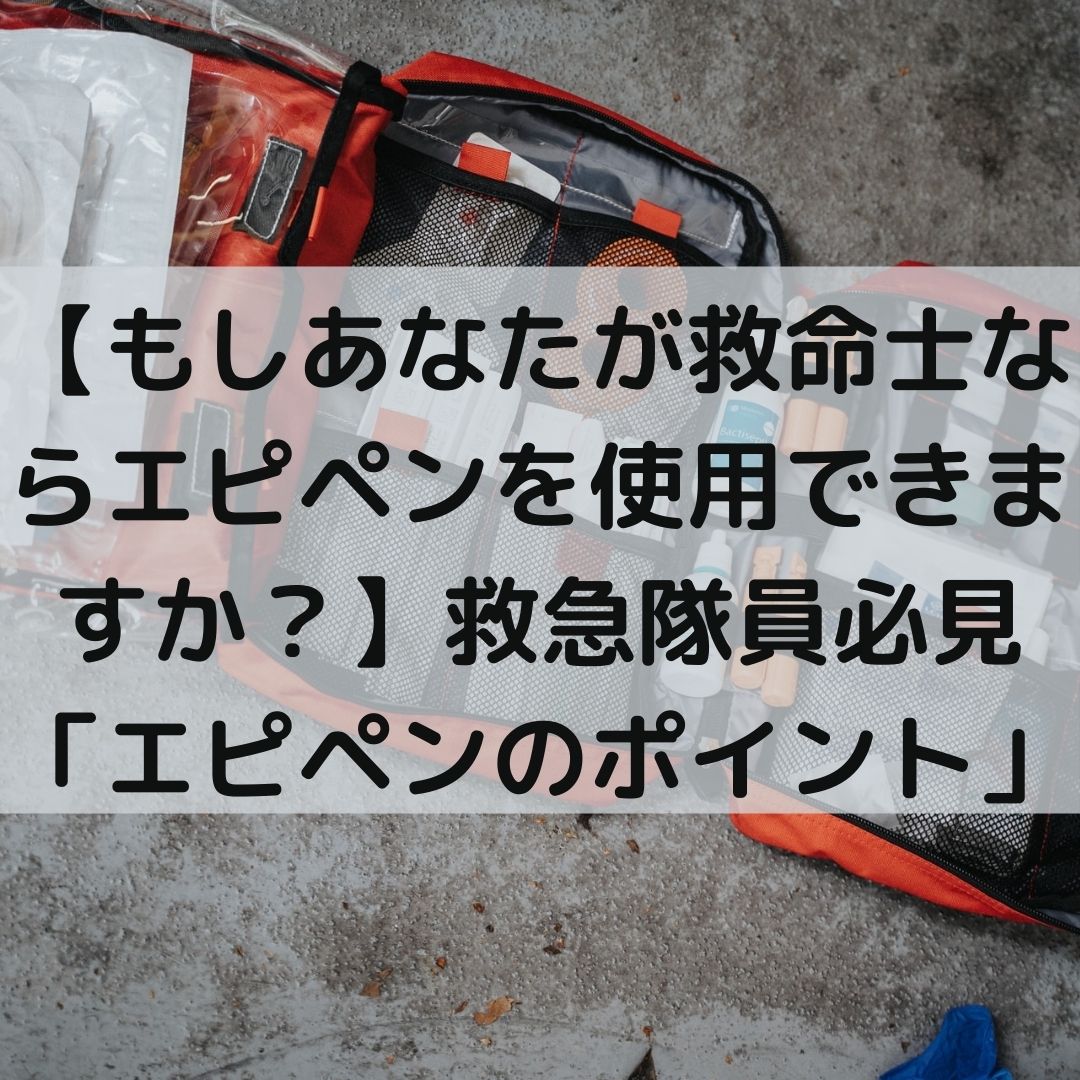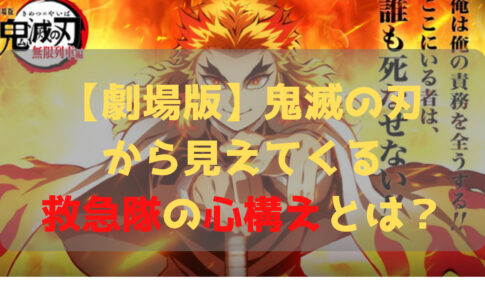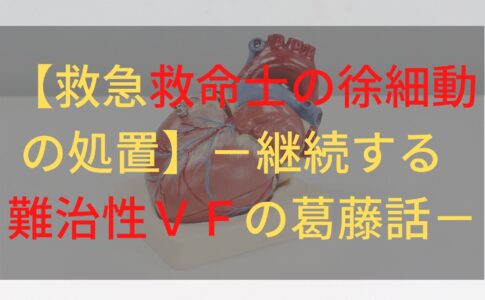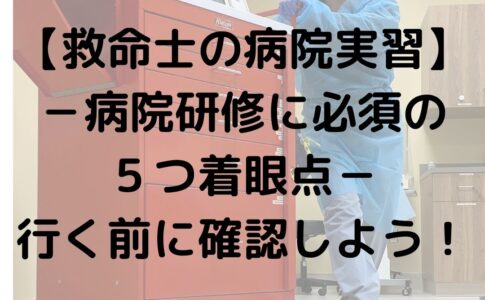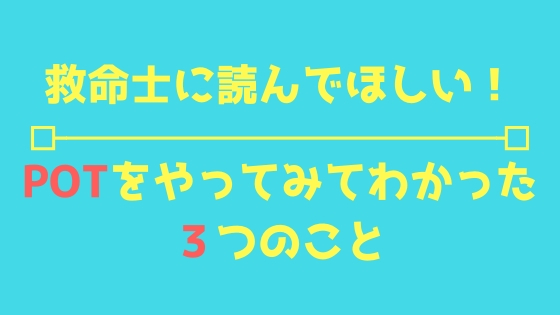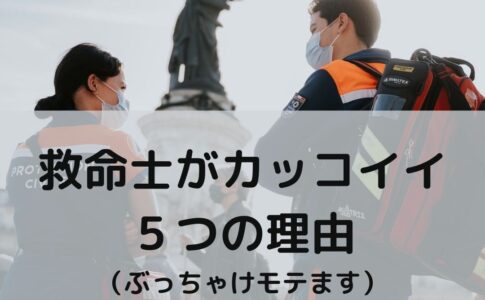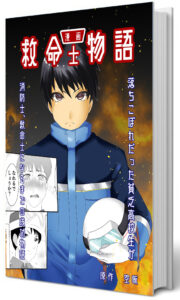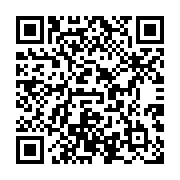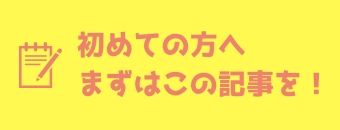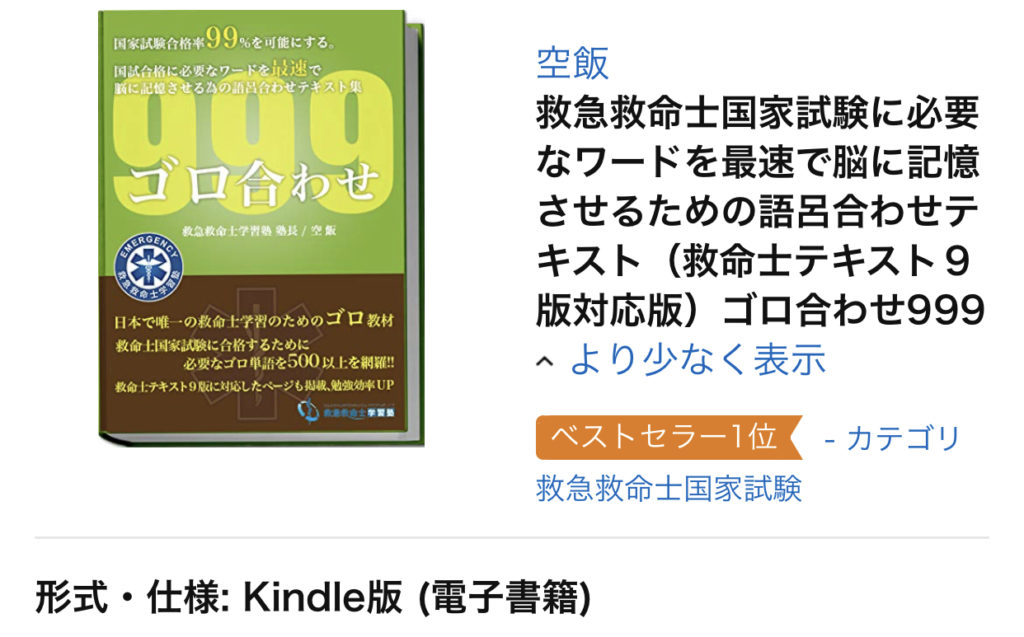LINEお友だち追加していただいた方が見られる特別な記事。LINEに「パス」とメッセージするとパスワードがLINEに送られてきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
空飯は19歳で消防士になり、26歳でエルスタ東京へ、
そして最年少で救命士となりました。
研修前には救命士国家試験合格レベルで、
最高に充実したエルスタ生活を送りました。
ですが、
最初から勉強ができた方ではありません。
勉強は超苦手で、高校は実業高校なのにテストで赤点とってたくらいです。
お前には才能があったんだろ?とも言われます。
僕はもともと勉強が得意だったわけでもなければ、
暗記が得意だったわけでも、
ましてや仕事ができたわけでもありません。
そんな僕でも自信を得ることができて、
研修所入校前に救命士国家試験合格レベルになりました。
エルスタ生活にもとても良い影響をもたらしました。
結局、勉強方法を『知るかor知らないか』なんですよね。
どんな人でも研修所入校前に国家試験合格レベルになれます。
やり方さえ学んでいけば誰でも自信をもって救命士になれる。
僕、空飯がどのように救命士になったのかを下記の記事では公開してます。
研修所入校前に救命士国家試験合格レベルになった空飯のリアル物語
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー