もくじ
救急救命士の位置づけと法律上の根拠
1. 法律上の免許職
救急救命士は「救急救命士法」に基づく国家資格であり、主な業務範囲は「傷病者の病院到着前における救命処置の実施」が中心です。
ただし、医師の指示のもとであれば病院内においても一定の救急処置を実施できます。看護師免許を持つわけではないため、看護師が行う医療行為すべてを行えるわけではありません。
2. 業務範囲(特定行為)
法律上、「特定行為」と呼ばれる行為(例:気管挿管、静脈路確保、アドレナリン投与など)については、一定の研修を修了し、医師の具体的指示のもとで実施することが認められています。
病院内であっても「医師の指示」「救急救命士が行える範囲の行為」であることが前提になります。
救急救命士が病院内で担うことが多い業務
以下はあくまで「一般的に想定される例」であり、病院によって運用方針が異なります。必ず病院のルールを確認してください。
1. 救急外来における初期対応の補助
- 救急外来に搬送されてきた患者さんのバイタルサイン測定(血圧、脈拍、呼吸数、SpO₂など)
- 傷病者の観察、状態変化のモニタリング
- 必要に応じて、医師や看護師の指示のもとでの酸素投与、AEDによる除細動、気道確保などの応急処置を補助
2. ストレッチャー移送や院内搬送のサポート
- 救急車から病院内への搬送や、院内での検査部署への移送など、患者の安全確保
- 状態に急変があった場合の対応(バイタルチェック、必要に応じて医師へ連絡など)
3. トリアージ(重症度判定)の補助
- 救急外来に複数の患者が同時に来院した場合の、重症度・優先度判断のサポート
- 患者の観察やヒアリングを行い、医師や看護師と協力してトリアージ業務を補助
4. 救急処置の準備や片付け
- 酸素ボンベや各種救急機材(挿管チューブ、点滴ルートなど)の点検・保守・管理
- 心電図モニターの装着準備、除細動器の点検
- 終了後の物品の片付け、消毒作業など
5. 特定行為に関する業務
- 病院内であっても医師の具体的指示があれば、法律で認められた「特定行為」を実施可能
- 特定行為の際は、必要な報告手順や記録を病院のマニュアルに従って行う
6. 教育・研修サポート
- 病院スタッフや研修医向けのBLS(一次救命処置)・ACLS(高度救命処置)のトレーニングやデモなどをサポート
- 実際の救急症例を踏まえた検討会やシミュレーション教育への協力
救急救命士が「できない」主な行為
1. 医師・看護師固有の医療行為
救急救命士の特定行為に含まれない処置(例:採血、各種カテーテル留置、複雑な薬剤投与管理など)は、法律上救急救命士が独自に行うことはできません。
医師の指示に基づく補助は可能ですが、実施自体が看護師免許や医師免許に限定される行為は担当できません。
2. 一般病棟での看護行為
バイタルサインの継続的な管理や、入院患者の日常生活援助などは看護師の業務です。補助的に行う場合はありますが、看護師と同様の立場でケアを担当することは認められていません。
3. 医師の診断・指示の範囲を越えた救急処置
特定行為であっても、あくまで医師の具体的な指示のもとで行うのが前提です。独断で処置を行うことはできません。
病院で救急救命士を活かすためのポイント
1. 医師・看護師との業務範囲共有と連携体制
「救急救命士がどこまでやれるか、やれないか」を病院全体で周知し、特に救急外来やICUなどで明確な役割分担を決めておくことが重要です。
2. マニュアル・手順書の整備
救急救命士が病院内で行う可能性のある行為について、医師の指示のパターンや報告ルートを明確化します。
書類や電子カルテへの記録方法、緊急時の連絡体制なども事前に定めておくとスムーズです。
3. 特定行為に関する研修や更新
気管挿管、静脈路確保、薬剤投与などを適切に行うためには、法定の研修や病院独自のトレーニングが必要です。
スキルを維持するため、定期的な実技研修やシミュレーションを取り入れましょう。
4. スタッフ間コミュニケーションの確立
救急外来では瞬時の判断とチームワークが求められます。医師・看護師・コメディカルスタッフと日頃から密に情報交換を行いましょう。
カンファレンスや症例検討会に参加し、救急救命士の専門性を院内にアピールすることも大切です。
5. 病院全体の教育・啓蒙活動への貢献
BLS講習や院内急変対応のシミュレーション教育など、救急救命士ならではの強みを活かして院内スタッフのスキルアップに貢献しましょう。
1.病院外でできること
1.1 地域医療・イベント医療のサポート
- スポーツ大会・マラソン・イベント救護での急変対応
- 熱中症、外傷、心停止などの応急処置
- 救急搬送判断・初期対応の補助
- 避難所・地域医療の救護支援
- 自然災害時の避難所でのバイタルチェック・応急手当
- 高齢者や乳幼児など、特別な配慮が必要な避難者への健康管理サポート
1.2 在宅医療・訪問救急支援
- 在宅医療患者のモニタリング・急変対応
- 在宅療養患者のバイタルサイン管理、緊急時の応急処置
- 医師の指示による搬送の判断・必要時の救急搬送対応
- 高齢者施設・介護施設での急変時サポート
- 特養・老健などの施設で入所者の急変時対応
- スタッフへのBLS指導・教育
2. 教育・トレーニング分野での役割
2.1 BLS・ACLS・PALS インストラクター
- 医療従事者向けの救命講習指導
- 病院職員、救急隊員、消防関係者へのBLS(一次救命処置)、ACLS(高度救命処置)のトレーニング
- 一般市民向けの救命講習普及
- AEDの使用方法、心肺蘇生法(CPR)、異物除去などの講習を地域で実施
- 学校・企業での応急処置教育
- 学校での防災教育、企業向けの緊急時対応トレーニング
- 社員向けのBLS講習(職場での救急対応強化)
2.2 シミュレーショントレーニングの主導
- 救急事例を想定したシミュレーション教育
- 医療チーム向けに急変対応シナリオの実技指導
- コードブルー(院内急変)の対応訓練
3. 災害医療・防災分野での貢献
3.1 DMAT(災害派遣医療チーム)への参加
- 大規模災害時の医療支援
- 被災地でのトリアージ、応急手当、傷病者搬送
- 医療物資の管理、被災者の健康管理サポート
3.2 地域防災・救急啓発活動
- 地域住民への防災教育・救命講習の普及
- 防災訓練時の応急処置指導
- 災害時の対応手順の教育(トリアージ、搬送方法の解説など)
- 避難所での健康管理・応急対応
- 避難所でのバイタル管理、感染症対策、救護サポート
4. 新たなフィールドでの活躍
4.1 航空医療・ドクターヘリ支援
- ドクターヘリでの患者搬送補助
- 医師・フライトナースとの連携による高度救命処置の補助
- 空中搬送時のバイタル管理・患者状態安定化
- 救急搬送中の応急処置サポート
- 搬送中の急変時対応、気道管理・酸素投与などの対応
4.2 医療搬送・患者移送のサポート
- 患者移送時のモニタリング
- 高度医療機器を使用した移送時のバイタル管理
- 転院搬送時の患者状態確認・応急対応
5. 特殊分野での可能性
5.1 法医学分野での協力
- 法医学検視の補助・記録
- 現場での遺体の状況観察、記録
- 搬送中の患者状態記録の保全
5.2 危機管理・リスクマネジメント支援
- 企業・団体の災害対策マニュアル作成
- 大規模災害や事故に備えた危機管理計画の立案・指導
- 災害時の応急処置体制の構築
6. まとめ:病院外・災害・教育分野でさらに広がる役割
- 在宅医療・訪問医療、地域医療の現場での支援
- 災害医療チーム(DMAT)・防災啓発活動でのリーダー的役割
- BLS/ACLS/PALSインストラクターとしての教育貢献
- 航空医療・医療搬送・特殊分野でもスキルを発揮できる
総まとめ
救急救命士が病院内でできることは、あくまでも「医師の指示の下で行う特定行為」や、救急に関する補助的業務が中心となります。
看護師や医師とは職域が異なるため、業務範囲をあらかじめ明確化し、連携していくことが不可欠です。
特に病院への初導入時は、担当部署や指示系統、報告フローなどをしっかり整備した上で、救急救命士の専門性を活かせるように環境を整えましょう。
まずは上司や医師、看護管理者とのコミュニケーションを図り、「何ができるか」「何を期待しているか」をすり合わせることが大切です。

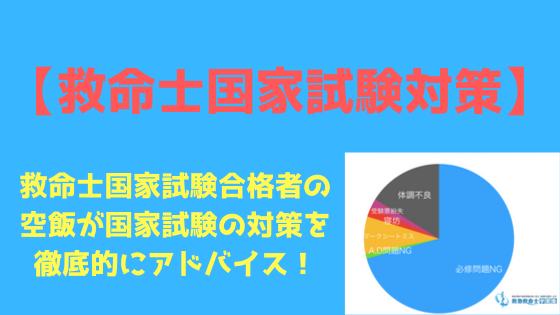
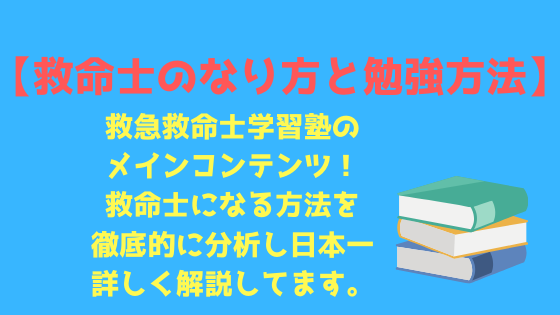
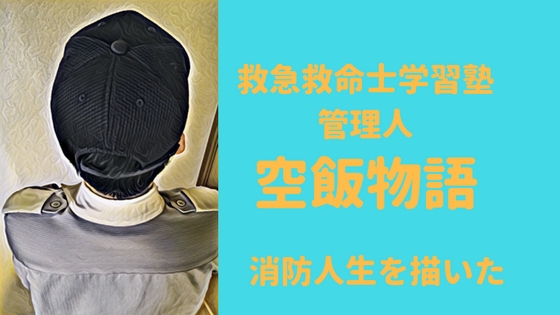




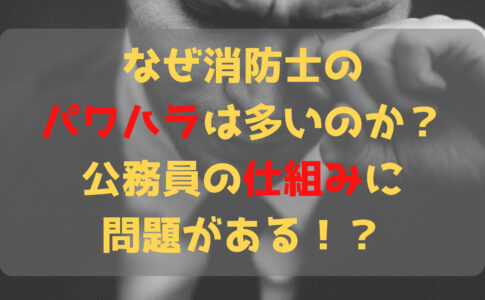
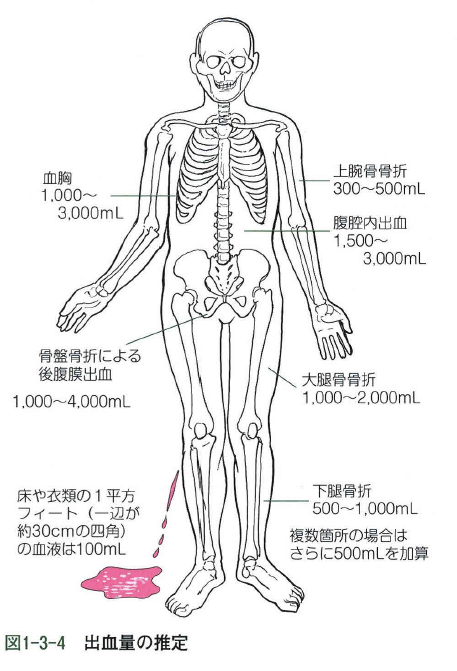

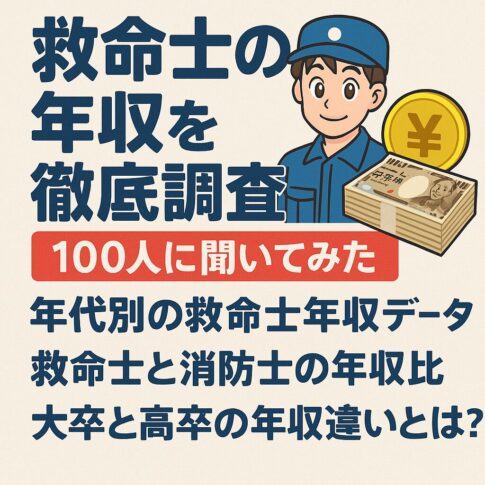

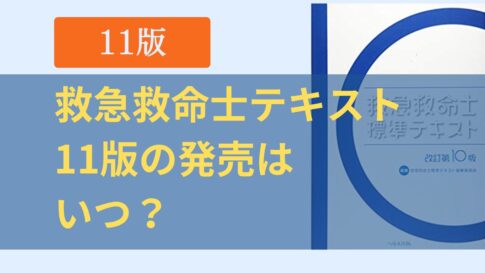
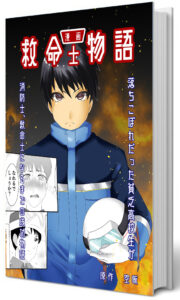
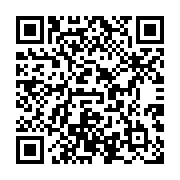

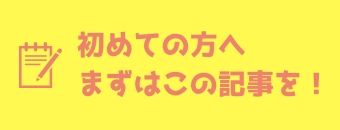
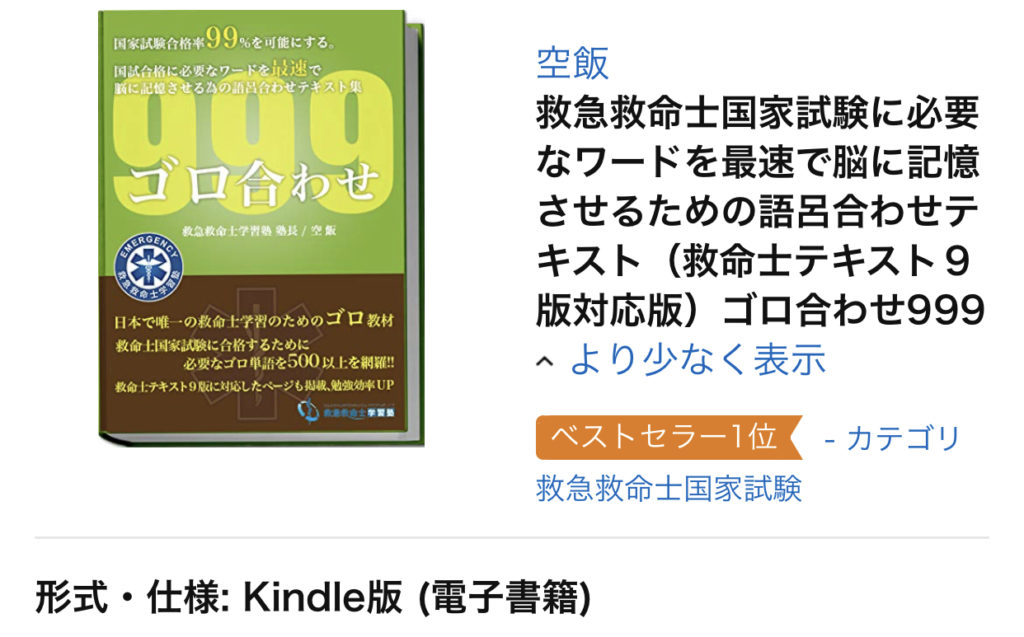
病院が救急救命士をはじめておく病院に勤務しております。
他に救急救命士としてできることはありますか?
斎藤さんコメントありがとうございます。さらに病院外でできることや教育トレーニングなど記事を追加させていただきました!